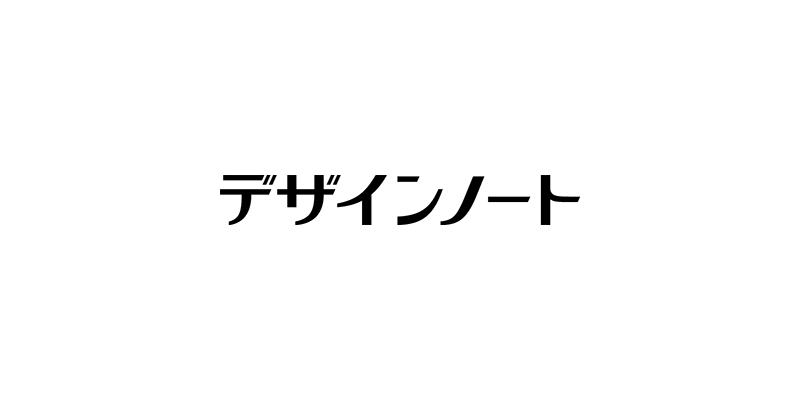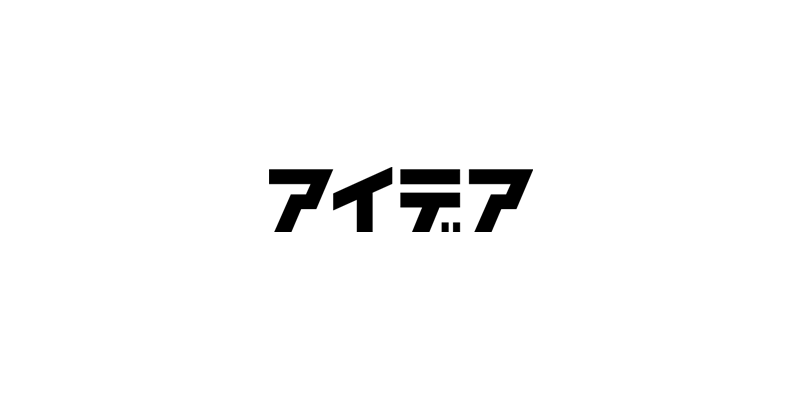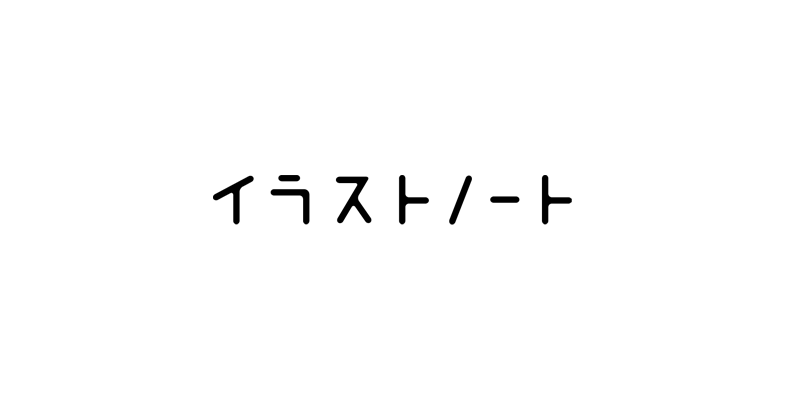「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の古川知宏さんに聞く、監督業の心構え<後編>
「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の古川知宏さんに聞く、監督業の心構え<後編>
監督とは「選ぶ」仕事
取材・構成:中村香住
2021年6月4日に公開され、一大旋風を巻き起こした『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(以下、劇場版)。今回は、テレビアニメから引き続き監督を勤めている古川知宏さんに、劇場版の制作に関することから、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(以下、『レヴュースタァライト』)という作品全般について、そしてチームで一つの作品に向かって共同作業を行う際の心得についてまで、縦横無尽にお話を伺うことができました。
前編では、劇場版に関する具体的なクリエイションのお話を伺うところから始まり、テレビアニメシリーズを含めた『レヴュースタァライト』全体について、監督の視点から語っていただいています。後編では、さらにもう一歩踏み込み、さまざまなアクターが関与している『レヴュースタァライト』という作品の中で監督を務める際にどのようなことを意識したか、チームで制作を行う際の仕事術から、クリエイターを目指す人に向けたメッセージまでをお話しいただきます。
>>前編はこちら

「舞台もの」というテーマがくれた強み
--ここからは『レヴュースタァライト』のアニメ制作全体の中で、共同で仕事を行った際の心構えなどをお聞きしていきたいと思います。そこで、もう一度真正面からお聞きしたいのですが、『レヴュースタァライト』には「ミュージカル×アニメーションで紡ぐ、二層展開式少女歌劇」というキャッチフレーズがあり、制作当初からミュージカルとの「二層展開式」だと決まっていた、その強みをアニメ制作にどのように活かそうと考え、実行しましたか。
古川:一番強みになったのは「舞台ものである」というテーマをいただけたことです。これを「縛り」だと思う人もいるのかもしれないけど、テーマって同時に強みでもあるわけですよね。舞台というテーマがあったから、テレビアニメ制作時の時に「無頼照明・ライト」の再現を思いつきました。1話の華恋ちゃん(愛城華恋)のバンクシーン明けからの、「みんなをスタァライトしちゃいます!」という決め台詞での「ダダダダダダダンッ!」と連続点灯するライト。あのカットが気持ちいいから好きって人が思いのほか沢山いらっしゃいました。あのカットは決めカットだから「アニメっぽい謎の光がキラーンッ!」とすることは簡単なんですよ。アニメーションの業界用語では「イメージ背景」と呼ぶのですが、実景ではない特殊な背景絵、例えば女児向けアニメの変身シーンがホワホワした素敵な空間になったりするじゃないですか。ああいった良くある表現も、やろうと思えばできますし、むしろ作る作業としてはとても楽です。ですが、その選択をした瞬間に「そのようなアニメ群の類型」になってしまう。舞台照明という選択をできたのは「舞台もの」というテーマを頂けたからですよ。
だから、世の中で変身シーンと言われているもの――業界用語では作中に何度も出てくるこのようなシーンをバンクシーンと呼ぶことも多いですが――も、「アタシ再生産」というキャッチワードの「再生産」から、「工場」のディテールを持ってきました。舞台の上でアタシが生まれ変わるのなら、「衣装」が縫製された方がいいよねと発想できる。舞台というテーマがあったから、「舞台照明」「工場」「衣装や武器の生産」と、この作品特有のディテールへと拡張が可能だったわけです。
デザインに限らずキャラクターやストーリーに関することでも、何か困ったら「舞台」というテーマに還元して立ち返って考えてみることが出来ましたし、あらゆるところに「舞台もの」の要素がたくさん散りばめられているから、必然的に作品を読み解こうという人が自然と出てきたのかもしれません。
--なるほど、「舞台もの」であるということから、さまざまなアイディアが広がっていったんですね。しかもそこには「舞台もの」だからという必然性がある。
古川:地下劇場のレヴューで謎の舞台装置が突然動き出すといったような「特別な空間」である設定も、「舞台」という単語が「これはある種の舞台セットなんだ」と視聴者の理解をカバーしてくれる。
前編でもお話ししましたが、「舞台」というテーマと実際にそれを演じた9人のキャストたちが、やはり作品を牽引してくれたのだと思います。舞台とアニメのキャストが同一であったことが、色々な説明を飛び越えて「スタァライト」の世界観の架け橋になったので。
キャラクター化されない、生身の人間としての「役者」
--そうしたキャストについていくつか聞いていきたいのですが、まずテレビアニメ制作の段階で各キャストのパーソナリティーをキャラクターに反映した部分があり、劇場版制作の際にも各キャラクターの進路について参考にするためにキャストに聞き取りを行ったと以前お話しされていたと思います。そうしたキャストへの聞き取りは、この二つの例以外にも適宜行われていたのでしょうか。
古川:テレビアニメ制作時は、僕が直接キャストに質問するよりも、どちらかというと武次茜プロデューサーが舞台の現場に行った時に、彼女たちが今この舞台でどういった気持ちで演じているのか等、色々な話を必然的に聞いてくることがありました。それによって彼女たち自身もですけど、同時に、「役者」という「職業キャラクター」に対する解像度がほんの少しですが上がったのはよかった。
どこか役者って存在も、職業として「キャラクター化」されているじゃないですか。ですが、当然「我々と変わらない同じ人間」でもあるわけですよね。そんな人たちが舞台に立った時に何を思うのか? 「舞台もの」作品としての当然のテーマがあるわけですが、稽古の時とかにちょこっと聞けたりした話が、樋口達人さん(脚本担当)や中村彼方さん(劇中歌作詞担当)をはじめとする色々なスタッフに示唆を与えてくれた。それは大きかったのではないかなと思います。
劇場版が愛城華恋の話になったのも、小山百代さんの華恋を演じることの難しさについての話が影響しています。舞台経験が長く、深い内面性のある小山さんに、作劇の都合とは言えテレビアニメの所謂「主人公的キャラクター」を演じさせてしまった。その結果、愛城華恋が「キャラクター」になってしまったと思います。当然、登場人物は全員「キャラクター」ではあるのですが、特に華恋は作り手の都合に影響された部分が大きかった。愛城華恋だけ人間じゃないままこのテレビアニメが終わってしまったと自分も思っていました。愛城華恋をテレビアニメの物語を進行するための舞台装置として機能させてしまった。「作られたキャラクター・舞台装置」である愛城華恋を演じるのは、舞台でもTVアニメでも、とても大変な事だったと思います。そう考えたとき、それ自体が「映画のテーマ」になると思い、劇場版に活かされました。つまり、テレビアニメ・舞台を通して小山さんという「生身の人間」が華恋とともに生きたからこそ、映画で「愛城華恋を人間にする」ことができた。それは自分にとって僥倖だったなと。キャストと一緒に走ってきたからこそ生まれた映画だったと言えますね。
--私がテレビアニメを一ファンとして見ていた時に、どうしても愛城華恋さんにだけ感情移入できなくて、なんかあんまり好きになれないなって個人的に思ってしまっていたんですよ。
古川:アニメーション上のキャラクターを演じていますからね。
--それでうーん......と思っていたのですが。
古川:どうですか? 映画以降の華恋ちゃん。シンプルに華恋ちゃんのこと好きになりましたか?
--なりましたね〜。
古川:それです。それがすべてです。
--ですので、「役者」という存在そのものがある種の「キャラクター」になりがちだけれど......というお話にはたいへん納得しました。
古川:医者や先生とか、職業が持つキャラクター性はテーマや物語上の仕組みとして機能するものですが、それが登場人物を追い込み、隙間に追いやってしまうこともあります。
今回は舞台装置として「主人公役」に追いやられてしまった愛城華恋が、人間として劇場版という「舞台」に上がった。しかもそれを演じているのは「小山百代」という一人の役者、と考えると舞台ものゆえのおもしろい仕組みにできたのかなと思います。
--しかもそこにすでに実際に演じている「役者」たるキャストたちがいたから、余計に、キャラクターも「人間としての役者」のようなものに肉薄しているのですかね。
古川:そうです。本当に、キャストが導いてくれたのだと思います。
--そんなキャストと一緒に仕事をする中で、「役者」としてすごいなと思った点について素朴にお聞きしてみたいのですが。
古川:これ、僕が見た夢の話していいですか? ある時、自分が舞台に立つ夢を見たんですよ。しかもなぜか(天堂真矢役の)富田麻帆さんと共演なんです。富田さん以外にも九九組のキャストいたかな? 稽古の時はなんとなく上手くこなしたのですが、観客の入った箱に立ちますってなった瞬間、お約束ですけど、僕キレイに全部台詞が飛んだんですよ(笑)。で、富田さんがジッと僕を見るっていうところで「はああああああ(汗)!!!!」と目が覚めました。
本当に怖かった。本当にこんな怖いことに立ち向かっているの?と思いました。素人が夢で見た程度で言うのはおこがましいことですが、すごい緊張感の中で演じているのだなと。劇場版制作前に行ったキャストへの「聞き取り」後に見た夢です。
「怖さ」に対する向き合い方、またそれに向き合っていられる彼女たちの勇気の源泉とはいったい何なのか? もしくは、演じざるを得ない人生を生きているのかもしれない。等々、色々なことを考えた結果として、その役者としての「怖さ」が、劇場版で華恋ちゃんが舞台上での死を迎える場面――映画館の観客という「舞台」の観客に気づいて怖い、というシーン――に結実したのかなと思いますね。
自分がわからない分野はスペシャリストにお願いする
--テレビアニメや映画のアフレコにおける演技指導の際には、何を意識して、もしくは演者のどんなところを引き出そうとしてディレクションしましたか。
古川:初めてアニメのアフレコを体験するキャストが多かったこの作品で、冴え渡っていたのは山田陽音響監督です。度々お話していますが、山田さんが「アニメらしい演技をさせようとしないほうが良いかもしれない」と提案してくれました。短期間に舞台がメインの役者さんに所謂「アニメらしい演技」を無理に演じさせようとしても大変だから、むしろ彼女たちの舞台での経験を活かした演技を、アニメを通して好きになってもらったほうが良い。それをキャラクターの個性にしたほうが良いとご提案頂きました。山田さんがとにかくキャストの持ち味をなるべく殺さないように腐心してくださったわけです。
『レヴュースタァライト』の企画を受けた時に、自分の経験値の足りない分野はキャリアのある先輩になるべく委ねたいと考えました。とくに音響演出の部分はやはりキャリアのある方にお助けいただきたいなと思っていたので、山田音響監督にお願いしました。自分の経験の浅い分野でクオリティを担保したい時には、スペシャリストにお願いするのが一番だと思います。例えば、セリフのトーンを落としたい時に、山田音響監督は、「こういう発声して、少し頭の角度をこうすると低い声出るから」とか、そういうことを丁寧にキャストにディレクションしていました。僕がなんとなく「もっと低い感じで」といっても彼女たちには上手く伝えるのは思った以上に難しいわけです。
--山田音響監督が古川監督の言葉を翻訳していたというか、具体的なところに落とし込んで、ディレクションしていたのですね。
古川:山田さんは実写の現場での経験もあり、演劇畑の役者さんともよく仕事されている。あと、やはり「演者に対する愛と尊敬」が深い方なのです。日本アカデミー賞最優秀録音賞受賞者の方ですからね。
同じように、背景美術と色彩に関しても経験豊かな方にお願いしました。「初監督作品において自分の経験不足を補っていただきたい分野」として真っ先に思い浮かんだ3セクションです。
キャラクターの感情線と映像のリズムを優先して「選ぶ」
--アニメーター出身の監督なので、アニメーターの仕事に対して色々言いたくなってしまわないのかなと思ったりもするのですが、アニメーター出身の監督としてどのようにアニメーターのみなさんと向き合っていますか。
古川:色々言いたくなりますし、ずっとあがいています。当然、修正が必要な内容で自分の描ける範囲なら手を入れます。スケジュールが無い場合は「このシーンはチェックさせてほしい」とかピックアップします。
結局監督は、「選ぶ」仕事なんですよね。自分にとって「ディレクション行為」は、その時現場にどのようなスタッフがいるのかを把握した上で、自分が今何をすべきかを可能な限り考えて選択していく行為なんです。そしてその「選び方」が監督の作る作品の個性にもなっていると思います。
例えば、絵コンテでは「必死に走っている」カットのはずが、上がってきたのは必死に走っているとは言えないモノだったとします。しかも修正しているスケジュールはない。そんな時に監督にはいくつか選べる手段があるんですよね。「絶対に必要なカットなので何とかして作画をやりなおす」も当然一つの手段です。ですが、描き直すとしても誰が描き直す? 古川がそれを作業している暇は無いでしょ?となった時に、即座に判断して「このカット自体をなくします。そして前カットの背景だけのカットに走る足音と吐息をつけて表現します」というやり方もできるわけですよね。
描ける人がいないのだったら無理に描く必要がないのでは? 別のことでも表現できるのでは? 更にはそれを上手く利用すればキャラクターの焦燥感よりが高められるのでは? ここは諦める代わりに絶対に別の大事なカットは守ろう!等々。ただ「省エネ」に徹するだけでは撤退戦にしかならないなら、どうやって「面白さ」に変化させるのか? 限定条件を演出に昇華させるには今何を選ぶべきなのか? そういったことを一個一個選択するのがディレクションであって、いわゆる監督とか演出家に必要とされている行為だと考えています。
当然、凄い作画メンバーを大量に抱えた現場でしたら、作品の作り方も違うと思いますし、どうしても必要なら、何を犠牲にしても挑戦して真正面から作画すべきだとも思っていますよ。
ちなみに例に挙げた場合では、「足音」などの効果音を付ける前に判断が必要になります。「走る」カットがある場合は、その絵にタイミングを合わせる必要があるからです。スケジュールと現場の能力を鑑みて絵コンテの段階で最初から「走る」カットを無しにしておくことも可能なわけですし、更にさかのぼって脚本会議の段階から「走るシーン」そのものを無くしておくことも出来る。更に突き詰めれば、「企画」の段階から何が実現可能なのかを想定することも可能なわけです。
根本的に「主人公が絶対に走ることが出来ないキャラクター」と設定したら、それが企画のテーマや物語にも成りうるわけですよね? そうやって常に段階ごとに「緊張感と責任」をもって「選び続ける」のが監督の仕事なのだと思っています。
--古川監督ご自身は、「選ぶ」際に何を優先していますか。
古川:キャラクターの感情線と映像のリズムを『レヴュースタァライト』では優先していますが、自分の力不足を痛感しています。中々自分の狙った気持ち良いリズムにならないです。
--『レヴュースタァライト』は、映像の動きだけではなく、「止め」の美しさにも大変こだわっていると思います。それはなぜでしょうか。
古川: まず「止め」の絵は作画が崩れづらいという前提があります。昨今のアニメーション業界は作品数の多さの影響で各社クオリティ維持に苦労しているのですが、そんな中「止め」のカットの活用はとても有効な手段の一つです。それと同時に「流れる時間のコントロール」のためという理由もあります。キャラクターが「ちょっと動く3秒」と「完全に止まっている3秒」って体感が全く違うんですよね。比較した時に「止まっている」3秒の方が長く感じるんですよ。コストパフォーマンスの管理と映像としての時間のコントロールを同時にしている感じですね。
あと、アニメって映像作品の中で、「本当に止まっている」を表現できる珍しい映像ジャンルなんです。実際の人間は呼吸しているので完全にピタッと止まる事は不可能なのですが、アニメの絵は完全に静止することが出来る。実写作品でも一時停止的に合成したりすることは技術的には可能ですが、それは違和感が生まれやすく、その瞬間「生きた人間」から「別のもの」に性質が変容したように見えてしまうこともある。アニメーションでは元々が記号として描かれているので、静止してもそのキャラクターの性質が変容することはないと考えています。静止したキャラクターでしか再現できない時間と感情表現が存在する。止まっている時の圧縮されている時間や心理描写・ディテール等の情報量によるキャラクターの華やかさのようなものがあるからこそ、動いた時の快楽がより強調されたりする。映像リズムの快楽とコストパフォーマンス、キャラクターの心理描写のために上手く機能するのが「止め」だと思っています。
だから、なぜ止めを選ぶのかと問われたら、キャラクターの感情と映像のリズムをお客さんに届けたいからですね。
一緒に「面白がる」ポイントを作る
--劇場版に関しては、単なるフィルムスコアリングではなく、フィルムスコアリング(絵に合わせて音楽を作る)→ミュージックスコアリング(絵コンテ・作画がカットを音楽に合わせる)→フィルムスコアリングの二段構えでやっていたと、劇場版劇中歌アルバムのオンライントークイベントでお話しされていたと思います。これは、かなり作曲家に信頼を置いていないとできないことであるように感じるのですが、劇伴やレヴュー曲の作曲家に対しては、どのような態度で向き合っていますか。また、制作途中でどの程度の相談のやりとりを行うのでしょうか。
古川:音楽プロデューサーである野島P(野島鉄平さん)・山田P(山田公平さん)のお二人には頭が上がりませんね。先ほどの音響演出等の話と同じですが、プロはプロ、餅は餅屋です。僕は音楽家ではないので、野島さんとか山田さんが信頼している作曲家の方でしたら、その人の良さをこちら側がキャッチするのも良い方法ですよね。
作品の作り方をとても大雑把に2種類に分けるとしたら、一つは封建主義的なトップダウンで、描かれた詳細な設計図をスタッフが実現し、その彫り上げられた美しい彫刻群が物語を物語るタイプ。もう一つは、上がってきたものの「出力」の良い部分・面白さをどんどん取捨選択して組み合わせていき、出来上がった彫刻の「並べ方」も面白がってしまうタイプ。僕はなるべく設計図も頑張って描きますし、身振り手振りも交えて伝えようと努力はしますが、どちらかと言われれば後者のほうです。
なので、自分にできないことはプロが高いレベルで出力したものを一度受け取ります。だから最低限、例えば劇場版の双葉(石動双葉)と香子(花柳香子)だったらシティポップとか、レヴューシーンのテーマは任侠映画でシーンピークはこのカットになりますといった説明をします。しかし、そこから先は一度プロに揉んでもらうのが一番です。出力されたものがどうしても自分のイメージと違ったら一度お戻ししますが、予想外の面白さが作品に生まれそうなら、絵コンテ側で調整したり作画であとから合わせる方を選びます。監督として選ぶ時に、プロとして間に立ち一緒に走ってくれたのが野島Pと山田Pのお二人でした。
--それは、例えば上がってきたもののイメージがちょっと違って、今回の場合はちょっと直してほしいという判断を監督がなさった時は、それを野島P・山田Pにお伝えになって、そこからそのお二人が適切に作曲家にディレクションしてくれたという感じですか。
古川:そういう場合もありましたし、「これはもう直接話したほうがいいね」という場合もお二人の方から率先して提案がありました。音源が上がってきた段階で野島さんから「今回の上がり、古川さんは気になるかもしれません」とすでにメールに書かれている事もありましたね。それはテレビアニメを一緒に作業してきたからだと思います。
面白がるところを見つける作業だと思うんですよね。僕は映像を作るために絵を描くことが多々ある仕事なのですが、音楽を作るのは僕には想像のつかない全く別の仕事だと思います。そんな他業種の方達と作品を作る場合は「一緒に面白がれるポイント」を共有するのが良いのではないでしょうか。劇場版の双葉と香子のレヴューだと、「曲調はシティポップなのですが、中村彼方さんの紡ぐ歌詞がデコトラと一体になってキャラクターの痴情のもつれを観客に届けるわけですね。デコトラのライトがビカビカと発光しながら、あなたの楽曲に合わせて走行する。絶対面白いです! つまりここがこのシーンの映像上でのピークです!」とお伝えする。そうすると作曲家の方も「ここが一番絶対面白くならなきゃいけないんだな」と、そのピークを一緒に目指すわけですよね。
別の仕事をする人とはとにかく面白がって、一緒に楽しめる、そして完成した時により「共同作業」だと思えるようになると理想的ですね。
お願いしただけ、作業しただけ、受け取っただけにならないよう、お互いの仕事を「キャッチする力」が大事なのかもしれません。当初フィルムスコアリングで進めていたとしても、こちら側が修正したほうがいいポイントがあったら絵コンテや作画を修正する理由はそこです。楽曲のここが一番面白いとなったら、それに合わせて絵コンテやカットの内容を直したほうが悔いは残らない。当然色々な方に迷惑をかけるので、「可能な範囲内で」ですが。
--一緒に面白がって、相手の一番いいところを活かすやり方をすると、作品自体のクオリティも高まっていきますよね。
古川:普通のアニメの現場では、劇伴やオープニング・エンディングの楽曲って、オンエアの大分前に納品されて終了な場合が多いです。僕が絵コンテと作画で参加させていただいたとある作品でも、先にすべてのアクションシーン用の歌唱曲がありました。楽曲に合わせたアクションシーンをスタッフ皆が頑張って作って素晴らしいものが出来たと思いますし、お客さんも非常に喜んでくれました。素晴らしいことだと思うと同時に、自分が何か作品を作る時は別の方法を選びたいとも思いました。楽曲先行だとどうしても「キレイにまとまり過ぎてしまう」と感じたんですね。そこで絵コンテに合わせての作曲作詞・フィルムスコアリングとなったわけです。テレビアニメのスケジュールと楽曲数を考えるととても大変な仕事ですが、楽曲チームと中村さんがそれに応えてくれたんですよね。とてもありがたい事です。
結果として、楽曲チームとの「一緒に走った感」が全然違って、その手応えがあったからこそ、劇場版に繋がったのだと思います。
--劇場版劇中歌アルバムの特典のオンライントークイベントを聞いていても、作曲家のみなさんが情熱をもってお作りになっていたことがすごく伝わってきましたね。
古川:今回は楽曲チームの皆さんの、情熱を「キャッチする力」もとても高かったのだと思います。
人を介するときに情熱の鮮度が落ちることが多いのですが、野島さんと山田さんのお二人は鮮度を維持し、作曲家陣に届けて下さいました。一緒になって面白がってくれて、一緒に出力を高めあえる特別な音楽プロデューサーなのだと思います。
情報共有のコネクションを多く持ち、伝え方を工夫する
--共同作業でいろんなアクターを介する中で、情熱の鮮度を保つのは大変なことですよね。監督自身は、情熱と鮮度を保ったまま共有するためにどんなことをしていますか。
古川:伝えるのに簡単な方法はありません。簡単な方法がないからには、「これくらいわかって当然だろ」と思って仕事をしないことが重要です。伝言ゲームって「伝わらない」ですよね。伝わらないからこそゲームになっているわけですよね。伝わらないという前提をもう少し意識して可能な限り「準備・用意」する。
--具体的には何を用意しますか。
古川:情報共有するコネクションを可能な限り多く持とうとします。「文字だけ」「絵だけ」「打ち合わせだけ」とならない様に工夫し、「面倒くさがらない」です。イメージのメモを用意し、絵コンテに詳細に説明文が描いてあったとしても更に注釈をつけ、直接打ち合わせできない場合は可能な限りビデオ会議をお願いする。ビデオ会議でも、画面共有だけではなく後ろにホワイトボードを用意して、絵を描き身振り手振りを交えた方が良いこともあります。
伝わらないからといって諦めるのはダメです。その伝え方も仕事の一つだと考えて、自分も模索中ですが「伝え方」を更新していく作業が必要かもしれません。デザイナーや作品を作る人たちは、実際に手を動かすことが一番の仕事ではありますが、「伝える」仕事も同じくらい重要だと思います。スケジュール等に追われたときに電話メールに返事しない等の「ディスコミュニケーション」になりがちですが、辛くても「相手と接点を持ち続ける勇気」が最終的に作品のクオリティを守ることになると思います。
これはデザイナー職だけでなく、制作などの事務方の仕事でも何も変わらないと思います。
--伝え方を工夫すること、確かにクリエイターにとって大事ですね。
古川:「何を実現したいのか」について、自分の中で明確化されているのが理想です。ですが、明確化されていないのなら、「はっきりしていない」ということをキチンと共有する。いわゆるブレストというか、誰かと一緒に「漂う時間」でしか生み出せないものもあるので。ただ、なんとなく付き合わせると相手がウンザリしてしまうので、「漂う時間」が必要なんだと相手にちゃんとわかってもらう。結果的にみんなで集まって描いたものが使われなくて無駄になったとしても「何かが違うとわかったから、別の選択肢を選べました」と明示する。選ばなかった意味も重要なのだと。
「尖った作家性」や「特定の用途の為の専門の道具・知識」には、幅が狭いことによって生み出された価値があります。同様に無駄な余地からしか生まれないものもある。高枝切り鋏のように用途が限定された価値もありますが、子供達にハサミを与えて自由に使わせるのにも「何が生まれるのか分からない」価値がある。その幅を広げる行為を「コスパ」「時短」みたいな単語にとらわれて蔑ろにするのだけは絶対良くない。時間は本当に大事ですし、実際無駄な会議もある。ですが同時に、「じゃあ自分は何か用意できていたのか?」「この2時間を最大限活かせるように立ち振る舞えたのか?」と自問する。
ディレクションやプロデュースに関わる人間が意識し続けないといけない事ですよね。「ターゲット層」「ユーザー」みたいな言葉だけが空中を漂う「時短な雰囲気会議」では生み出せないものもある。
誠実に、恥ずかしがらず、真剣に臨む
--しかし、今回お聞きした人たち以外にもさまざまなアクターの方がたくさんいらっしゃる中で、同じ情熱を持ちながら一緒に共同作業していくのは、すごく大変なんだろうなと想像します。
古川:ただ、どんな業種でも一定以上のクオリティを出力されている方は仕事に対して誠実な印象があります。誠実さに基づく性善説がうまく機能したのだと思います。先行して真摯に舞台に向き合ったキャストや舞台スタッフ、アニメーションの現場スタッフ、音楽チーム、それぞれに誠実に仕事に向き合う方が多かった。
誰かの熱量が他のスタッフの熱量を呼び起こすというありがたい現場でした。そこは恥ずかしがらずに旗を振り続けてよかったと思っています。
「恥ずかしがらないこと」はとても難しいですが、大事な事だと思います。会議の席で「これ言ったらかっこ悪いかな」とか「あんまり冴えたアイデアじゃないかな」と思い込みがちですよね。実際、無駄な発言しないほうが良い時は黙っていたほうがいいですし、くだらない幼稚な発言でも自分がするべき発言だなと思ったら言えばいい。「感覚的にちょっと苦手なので私はこのほうが良いと思います。理由はちょっと言葉に出来ませんが次までに考えてきます」と理由が不明確な事もセットで言う。以前に違和感を表明した人間が納得のいく理由を表明出来たなら、それは価値のある発言です。恥ずかしがらないで提案したり意見を表明するのは勇気が必要ですが、次につながることもある。自分の好きなものに対し誠実に、勇気をもって発言することは、とても重要なことです。
--「誠実」さが一つのキーワードなのかなと思いました。『レヴュースタァライト』の制作現場でも他の人の誠実さをリスペクトし合うことで熱量が高まっていったのかなと。
古川:餅は餅屋ですから、任せるところはおまかせする。その上で恥ずかしがらずに意見を表明する。
「発言しないと仕事してない雰囲気だから」、こんな理由で発言するのは一番意味がないと思います。たまにしか発言しなくても面白い人の意見はすぐわかってしまう。勇気をもって真剣に臨んだ場数がその人の出力の精度を磨いている。あらゆる大人の仕事において同様の事が言えると思います。
「足りない」部分が「自分の仕事のテーマ」になる
--それでは最後に、今後挑戦したいことについてお聞かせください。また、これからアニメ制作方面に進もうとしている人へのメッセージをお願いします。
古川:今後挑戦したいことは、ちょっと含みもありますが「話の筋がちゃんとわかる」と言われるアニメ。だから新作(「タイトル未定作品」)では、脚本をミステリ作家の斜線堂有紀さんと共作しています。自分のウィークポイントに一つずつ挑戦してゆくのが目標です。ロジックの力のある作家の方と映像体験に振り切った自分とがセットになったときにどんなものが生まれるのか。餅は餅屋で、得意な人と一緒に新しく挑戦していくようにしています。
自分には一度に大きく前進出来るような吸収力も才能もないことが、アニメーター時代からわかっていました。下手くそな自分に出来るのは「今回このカットは衣服のシワをテーマにシワだけ頑張ろう」みたいな小さな挑戦だけです。監督になった今でも同じで、じゃあ古川のアニメは話の筋がわからないって言われたら、ミステリ作家の方をお招きしてオリジナルアニメを作ってみようと。
僕がラッキーなのは才能がなかったことです。アニメーション業界に入って5年目くらいで色々と限界を感じていたところで、特別なアニメ監督である幾原邦彦さんとお仕事する機会を得ました。幾原さんから学んだこと、自分に出来ること、自分の好きなものを組み合わせたら何ができるか? 才能がないがゆえに色々な選択肢とかマテリアルをチョイスする癖がつきましたし、得意なことは得意な人に任せることも出来るようになりました。
今自分にないことを嘆くよりも、できることを活かして課題をクリアする。着実に自分の手元の実績を積み上げていくことが重要なのかなと思っています。「足りない」部分はいつだって「自分の仕事のテーマ」になる。
--本日はありがとうございました。
2022.06.24