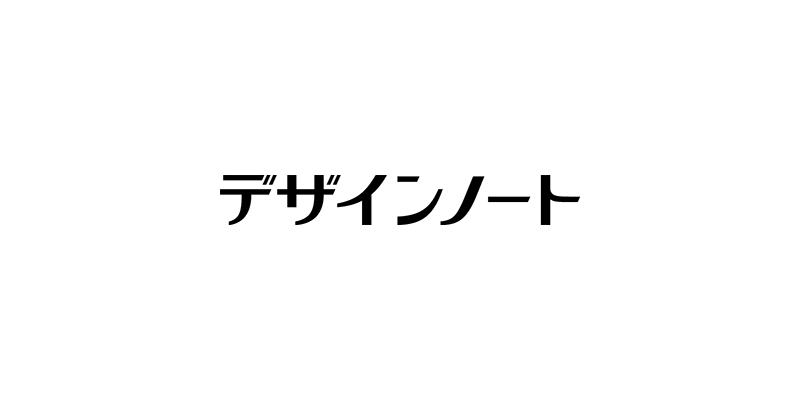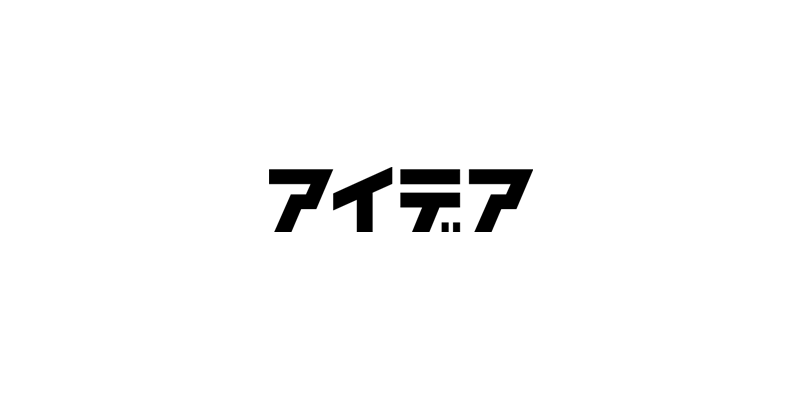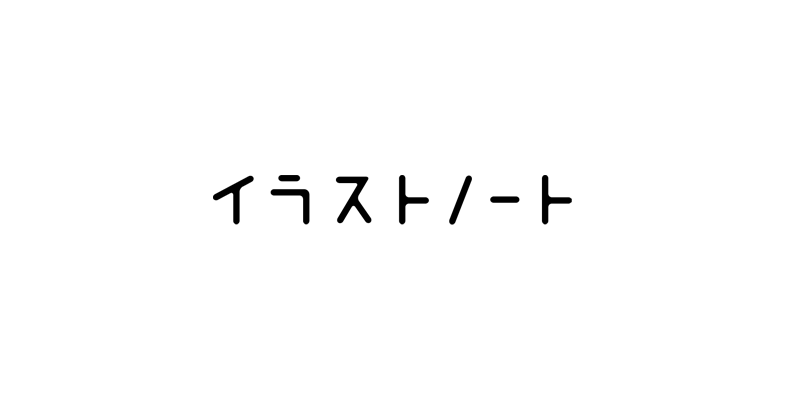「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の古川知宏さんに聞く、監督業の心構え<前編>
「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の古川知宏さんに聞く、監督業の心構え<前編>
監督とは「選ぶ」仕事
取材・構成:中村香住
2021年6月4日に公開され、一大旋風を巻き起こした『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(以下、劇場版)。今回は、テレビアニメから引き続き監督を勤めている古川知宏さんに、劇場版の制作に関することから、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(以下、『レヴュースタァライト』)という作品全般について、そしてチームで一つの作品に向かって共同作業を行う際の心得についてまで、縦横無尽にお話を伺うことができました。
前編では、劇場版に関する具体的なクリエイションのお話を伺うところから始まり、テレビアニメシリーズを含めた『レヴュースタァライト』全体について、監督の視点から語っていただいています。後編では、さらにもう一歩踏み込み、さまざまなアクターが関与している『レヴュースタァライト』という作品の中で監督を務める際にどのようなことを意識したか、チームで制作を行う際の仕事術から、クリエイターを目指す人に向けたメッセージまでをお話しいただきます。

映画館での「体験」がもつ幅
--「全部説明しないと伝わらない」という風潮を強く感じる現在の世の中で、これだけ抽象的な表現を用い、かつキャラクターの感情でドライヴするような映画を制作できたのは凄いことだと思います。なぜここまで思い切って、説明された話の筋を追うタイプの映画ではなく、「歌劇体験」映画の方向性に振り切ることができたのでしょうか。
古川:まず、今自分にできることを選んだ結果、公開された映画の形になりました。自分の中にも、アニメ映画然としたアニメ映画というものが、やっぱりあるんですよね。例えば、高畑勲さんの『おもひでぽろぽろ』とか。高畑さんはいわゆる「撮影所時代の邦画」的なものをアニメにおいて成立させられた数少ない人だと思っています。そのような映画を自分が成立させられるのかと考えた時に、答えは「否」だなと思って。
あとは今の時代のお客さんに何かを届けようと思った時に、他のやり方もあるのではないかという思いが自分の中でずっとありました。
--邦画的なアニメ然とした映画とはまた違ったやり方があるだろうってことですよね。
古川:そうですね。アニメも実写も関係なく、映画館で受ける映像体験としては、もっと色々な種類や幅があったはずですが、その幅が失われつつあるのではないか、と。でも、失われているということはつまり逆説的に「価値がある」とも思ったんですよね。先ほど言ったようなアニメ映画然としたアニメ映画を作るとなると、とても時間と予算が足りないし、自分のキャリアと知名度的に著名なスタッフを捕まえられるわけでもない。「さて、どうしよう?」となった時に、限られたスタッフ・自分に実現可能な事・演劇というテーマ、それらをスピード感をもったフィルムとしてお客さんに届けるには「体験に振り切るしかない!」と思いました。なぜ実現できたのかというよりも、僕にはその選択肢しかなかったというのが正直なところですね。
あと、奇跡的に、ブシロードの武次茜プロデューサーであったりとか、音楽のポニーキャニオンの野島鉄平さんであったりとか、テレビを通して一緒に歩んできたチームの人たちが「もう一度みんなで走りきろうよ!」っていう気持ちでいてくれたからだと思います。委員会も含めた皆さんがこういったアニメ映画を作ることを許してくれたのは、ありがたい状況だったなと思いますね。最初から今のような「攻めた」アニメ映画を作りたいって言ったら、許可は出なかったんじゃないかな。テレビを経て、「まだできることがあるはず、何をやる?」となったから、このような選択肢を選ぶことを許していただけたのかな、と。
--先ほど、映画館での映像体験にはもっと幅があったはずだとおっしゃっていましたが、監督ご自身の原体験としてはどのようなものがあるのでしょうか。
古川:細かい映画はいっぱい挙げられるのですが、作品名にとくに意味はないかなと思っていて。作品を挙げるならいくらでも......僕、北野武さんの映画が好きだし、やはり『旧劇場版エヴァンゲリオン』を映画館で目撃できた人間なので、そういった映像体験は大きかったです。
ただ、『レヴュースタァライト』の企画を受けた段階で『ラブライブ!』をはじめとするリアルライブとの共存作品がすごく力を持っていました。僕はライブとかには全然行かない人間で、映像っ子だったんですね。理解できなくはないのですが、なんでアニメという「映像」が好きなはずなのに声優さんのライブに行くのだろう、と不思議に思っていました。まあ、アニメが好きな人はその「映像」が好きなんだ、という勘違いですよね。『レヴュースタァライト』の仕事を受けたのはそんなリアルでの「体験」とセットの作品造りが気になったからという側面もあります。企画としてアニメキャストが舞台でも同様に演じる作品を一緒に造る体験をしてみたかった。
結果としてどうだったのかというと、一緒に作品を作り上げる仲間であるキャストさんが舞台で演じ、ライブで歌うのを目撃して「なるほど!これは元気になる!」と衝撃を受けました。「映像」とは違った軸として「作品やキャラクターに対する愛着」って、こんなにすごい魅力を発揮することなんだって、齢30後半で初めて知ったんですよ。本当にびっくりしました。自分が関わってきた作品のキャストを尊敬しているし、キャラクターにも愛着があるのですが、映像とは別の「体験」もあることを痛感しました。
ただ、だからこそ映画を作る時に、今の若いお客さんがリアルライブとは違った映像の「体験」はしてるのかなと思ったんですよ。これはテレビアニメの1話から半分意図していたことなのですが、話の筋を追うアニメがたくさんあるなか、レヴューの第1話ってキャラクターの感情と音楽で押し流す「体験型」のアニメなんですよ。話数の後半、レヴューシーンが始まってからオープニングも含めて約8分近くかな、音楽がかかりっぱなしなんですよ。しかも、劇伴の音楽じゃなくて「歌もの」の楽曲がずっとかかりっぱなしのままシームレスにオープニングテーマに繋がる「映像体験」になっている。そんな映像体験を今のアニメの若いお客さんたちはあまり経験していないみたいなので、劇場版はそれを更に拡張してフルスイングした感じです。個人的には自分の得意なレンジの作業ではあります。
--すごく面白いですね。当初は声優さんのライブとかなんで面白いんだろうって思われていたところから、ご自身も「元気になる」という実体験をされて。
古川:「なにこれ、楽しい!」って、更には「危険だ!」と衝撃を受けました。ミュージシャンのライブ映像とかを見るのは好きだったのですが、どちらかと言うと、演出面のこだわりを見ちゃっていたんですよ。ライブとか舞台っていうものを「体験」として楽しんだことがあんまりなかったので、すごく勉強させて頂きました。そんな新しい体験を活かしつつ作ったアニメが逆輸入されて、2ndライブ(「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』2ndスタァライブ "Starry Desert"」)でのレヴュー再現に結実した時に「あ、うまくいくところまでいったな」と思いました。
--当初から意図されていたミュージカルやライブでの展開とアニメーションの展開との二層展開式が、うまく転がっていったというか。
古川:そうですね。ライブでは自分たちがアニメで観たものが可能な限り再現され、舞台ではアニメキャスト自身が役者として演じるというコンテンツは中々珍しい体験になったのだと思います。そう考えた時に、ブシロード、ポニーキャニオン、TBS、オーバーラップ、ネルケプランニング、その他製作委員会のあらゆる方を含めて、みなさんのチームがこの作品でしかできないゴールに向けて走ってくれたことに対してとても感謝していますね。「2ndライブすごかったよね!」と、当時生で見た人はそう言いますね。
--そうしたご自身の体験も経た上で、劇場版ではより抽象的な「体験」型映画を観客に届けたわけですが、その中でも既存の「レヴュースタァライト」のファンが置いてけぼりにならない映画にするために、何か工夫したことはありますか。
古川:そこは、キャストの9人と劇中歌作詞の中村彼方さん・脚本の樋口達人さんがつないでくれた部分が大きいと思います。
観客が置いてけぼりになっていない理由って、キャストがまずつないでくれているのだと思います。テレビアニメ、ライブ、舞台を通して、お客さんがやっぱり九九組の9人とキャラクターに愛着を持ってくれているんですよね。ただ声優として演じるだけではなくて、ライブでは歌い、舞台でも演じることによって、キャラクターとキャストの接近感が高いので、お客さんが九九組を追いかけやすいというか、愛着を持ちやすくなっている。強烈な接着点になってくれているのはキャストで、どこまでいっても「レヴュースタァライト」っていうのはキャストの9人に支えられている。
そして彼女たちの全ての歌詞を紡いでいるのが彼方さん、アニメーションの劇中で彼女たち発する言葉を僕と一緒に走って作ってくれているのが樋口さん。二人を始めとするすべてのスタッフの仕事がキャストと一緒にお客さんの感情をつないでくれたのだと思います。偉大。
オマージュは次の表現に飛ぶための「ジャンプ台」
--少し話が変わるのですが、本当はやりたかった・引用したかったけれど、最終的にはフィルム上では削ることになった、過去映画からの引用表現は何かありますか。
古川:僕がインタビューで引用とかオマージュっていう単語を使ってしまったせいで、勘違いされがちなのですが、したくてやっているわけではないんですよ。つまりそれは目的ではないです。作品を作るための行為・表現手法としてやっています。だから、「やりたかったオマージュ」みたいなことはないですね。つまり必要に迫られない限り、その選択はチョイスしないんですよ。「面白がって引用する」みたいな事ではないです。
映画とか歌とか詩とかいろんなものが持っている、その時その瞬間にしか流れない空気というものがある。それを「因数分解して出力し直す行為」を、僕は「オマージュ」と言っています。
僕にとっての「技術」として説明するなら、オマージュというのはベース値が高いんです。つまり土台があるから、最初から40点位取れるんですよ。因数分解すると、その作品の演出力の基礎になっている組み立てが一度自分の中で手に馴染むんです。それを「レヴュースタァライト」だったらどう表現するかってことで、別の絵に置き換えたりとか、ここでアップにいくのではなく、むしろ顔を見せないほうが「スタァライト」っぽいよな、とか考えていく。自分の中での、画面を成立させる力みたいな、ベースを一回引き上げるために、一度引用してみるのはとても効果が高いことなんですね。自分の引き出しが増える。
つまり、「引用すること」が目的なんじゃなくて、画面の強度を上げたりとか、さらに自分らしい別の表現にジャンプするためにやっていることと言ったらいいでしょうか。「ジャンプ台」って考えたらいいのかな。次の表現に飛ぶための台だと思っていますかね。
結局実写も含めて他の映画監督や作家の方が、普通、且つ無意識にしていることと大差無いことです。
--とても失礼な質問をしてしまったんですけども、オマージュについて技術面も含めた監督のお考えを聞けてよかったです。
古川:いえ、僕の言葉選びが悪いからだと思います。
あと、これに関しては半分面白がっていて半分否定的なのですが、みなさん「答え合わせ」したがるんですよ。
--ああ、したがりますね。
古川:ただ、僕からすると「正解とは?」という気持ちです。色々なところでお話ししているのですが、「わかります」って、自分の口癖であると同時にわかったつもりになりたい人へのちょっとしたジャブでもあって。
みんな作品を「なるべく簡単にストレスなく所有したい」と言いましょうか。「わかった自分」が重要になっちゃっていて。トロフィーを棚に飾りたいみたいな。だから検索して出てきた情報にすぐ飛びついちゃう。「幾原さん」「ウテナ」「ピングドラム」「庵野さん」「エヴァ」みたいな。それって何かの「答え」なの? ただの「情報」では?と。
作品とあなたの間(あいだ)に何かが生まれたかでしかないのに、「情報」と「正解探し」に終始しているのは、僕からするとちょっと不思議。
ちなみに「考察」みたいな行為を否定しているわけではないですよ。「考察」は自分と作品の関係を深めたり変容させたりする豊かな楽しみ方だとも思います。でも同時に「あの映画、良くわからなくて自分には合わなかった、ツマンナイ」でも良いと思います。
--そうですね。最近の消費のスタイル、作品を楽しむスタイルについては、今のお話を聞いて色々考えさせられてしまいました。
古川:良い悪いではなくて、どちらかというと「そういう時代に何を作るか?」になっているというのが自分としては正直なところです。お客さんが悪いなんてことはない、お客さんの楽しみ方は自由なので。
ただ、考察をはじめとする「幅」を持って楽しんでもらえるのは珍しい作品なのだと思いますし、それも一つの作品のカラーとして、次はどんな体験にお客さんを引きずり込めるかを考えるのが自分の仕事だと思っています。
「演劇」を表現するうえでの工夫
--『レヴュースタァライト』は舞台をテーマにした作品ですが、演劇は、もちろん複数回公演されるものもありますが、やはりその時その時で違う演技がなされたり、その時にいるお客さんの反応で異なる演技がなされたりすると思うので、かなり一回性が強いものだという認識・イメージがあります。そうした一回性の強い演劇をアニメというフォーマットで表現する難しさについて、どんな工夫をしましたか。
古川:一回性が強い演劇というものをテーマにする時に自分が腐心したのは、それを作品の構造とかキャラクターの大仕掛けにしたことです。
「演劇の一回性」という性質を多くの人は普段から意識しているでしょうか? 言われてみれば「そうだよね!」と感じるとは思いますが。
定期的な観劇習慣のない普通の人からすると、「舞台」という単語から想起されるのは、とても大雑把に言うと劇団四季とか宝塚歌劇ではないでしょうか? 「演劇」の印象がそれぐらいに絞られてしまうぐらい「舞台観劇」ってハードルの高い趣味だと思います。あとは2.5次元が人気あるくらいで。「一回性」のようなある種の「性質」までは想起できるのは演技経験者や観劇趣味のある方だと思います。
なので、「レヴュースタァライト」の企画を受けた段階で想定した視聴者も当然「観劇習慣のない普通のアニメ視聴者」なんです。そんな視聴者に「演劇の一回性・同じ舞台はない」という「性質」を伝えるためには「キャラクター」にしてしまった方が良いのではないかと考えたのが「大場なな」です。
「キャラクター」にすることによって、「演劇の一回性」も一般の視聴者に伝えやすくなりますし、同時に大場ななの魅力を加速させることもできるわけです。
--「舞台」をテーマにしている作品なので、演劇にまつわるシーンが色々と出てきますが、とくに演劇学校って一般の視聴者にとっては非日常感があると思います。その中で日常感というかリアルさを意識したのはどこですか。
古川:「非日常の中のリアルさ」ってあるじゃないですか。演劇学校の中でもお客さんが「ギリギリ想像できる日常」ってあると思うんですよ。例えば、B組(舞台創造科)の大道具の子と次の教室に移動するために着物のまますれ違うとか。あれって、実際にあるかどうかは別として、僕らみたいな一般人レベルでも想像できる「ありそうなシーン」じゃないですか。難しいもので、宝塚歌劇団のような本当のリアルな舞台学校みたいなものを描いたらその瞬間、非日常すぎて逆にリアルに見えないんですよね。そこを調整するのも重要な仕事です。
もちろん、演劇学校という舞台設定を徹底的に調べて、丁寧に描写するやり方もあります。よくドラマとかのお仕事ものであるやつですね。でも、それは実写ドラマだからできるリアリティの深度であって、アニメーションで全部描写するのはとても難しいです。そのようなリアルな描写に尺を割くのと、レヴューシーンも含めてキャラクターに愛着を持ってもらうのとを天秤にかけた時に、この作品では後者を選択しました。そういった観点で作品のリアリティの深度をチョイスしていますね。なので、テレビアニメであまりやる事のできなかった演劇学校のディテールを劇場版では盛り込む予定でしたが、尺の関係で切ることとなりました。
マスコットキャラクターは作品に「余地」を生む
--これは私がどうしても聞きたかった質問なのですが、Mr.ホワイト、スズダルキャットの誕生理由・経緯について、またなぜそれぞれのキャラをそれぞれの舞台少女にあてがったのかが気になります。
古川:Mr.ホワイトみたいなマスコットキャラクターって、作品に必要かと言われれば必要ないです。ですが、必要ないから不要だとなると、作品に幅がなくなっちゃう。「余地」 なんですよね。「余地」がないと、ストーリーがドラマのシリアスな部分にだけ集中してしまって、お客さんの視聴体験として疲れてしまう。
なので、レヴューでバチバチやっても「日常パートで殺伐としない」と決めていました。バチバチに戦った相手が教室でもギスギスしているとお客さんはちょっと耐えられないんですよ。徹頭徹尾殺し合いをする作品だったら逆にそういう作品として受け止めていただけるのですが、中途半端なギスギスは視聴体験を損なうだけだと考えました。生身の役者の演じるものなら別なんですけどね。アニメーションのカリカチュアされたキャラクターって、嫌なやつは徹頭徹尾嫌なやつにしか受け取れなくなっちゃうので。
ただ、同時にアニメーションはこういったマスコットキャラクターによる中和が得意なジャンルでもあります。雑談レベルで小出君(小出卓史副監督)が「(神楽ひかりのレヴュー服に)クマが付くんですよ!」と言い出して、僕は「あ、これ猫じゃなくてクマなの〜?(笑)」みたいなやり取りをしたんですね。名前は2人で決めたのですが、僕は、「Mr.なんとか」って外国人の普通の名前。小出君は「ザ・ホワイト」。じゃあもう合体して「Mr.ホワイト」だなって(笑)。いつの間にか生み出されていたキャラクターではあったと思います。
一個生まれると、それに対してライバルキャラであるスズダルキャットがいた方がいいんじゃない? みたいな話にもなりまして。「ひかりちゃんのキャラのライバルってことは、このキャラはまひるちゃん(露崎まひる)のになるよね」みたいな。僕や小出君とか、スタッフの内輪の楽しみの部分が拡張していった感じですね。キャラクターに付随したものは出てきたら演出上利用した方がいいよね、というのが僕のスタイルなので、必然的にテレビアニメの5話や劇場版のレヴューに登場することになりました。お客さんに愛着を持ってもらうマスコットキャラクターであると同時に、キャラクターの演出上の 「仕組み」 になるものができるといいかなと思って腐心した次第です。
--Mr.ホワイトがスゴウデのスパイ、スズダルキャットがそのライバル的立ち位置というお話は以前されていたと思いますが、カニハニワにはどのような設定があるのでしょうか。
古川:カニハニワには特別な設定はないですね。本当に僕がただ絵コンテで「変なものがあった方がいい」ってことで描いていただけなんですよ。本当は華恋ちゃん(愛城華恋)に何かキャラクターをあてがう気はなかった。主人公に要素を付けすぎるのはちょっと良くないなって個人的に思っていまして。ただ、僕が1話のコンテでカニハニワを描いたら、デザイン協力の谷紫織さんが「ショルダーかばんにします」って。「あああ~可愛いから〜いいよ!」みたいな感じです(笑)。だから、華恋がカニハニワに言及することはないです。
--ないですよね。
古川:それはやはり後から付随して生まれたデザインなんで。でもこういった余地を持たせておくと、後から何か利用できるのは便利ですよね。今回は舞台・ライブ・アニメ・ソーシャルゲームといった複合展開のコンテンツでしたので、デザインの中にディテールとしてそういったものを混ぜ込んでおくと後から引き出せる余地になる。たとえば、スタリラ(スマートフォン向けゲームアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』)でカニハニワと華恋の出会いのストーリーを作って展開するとか。ゲームとか舞台で後から突然足されたモノって場合によってはお客さんがちょっと冷めちゃうじゃないですか。
あ、でも、「カニ」って書いてあるTシャツを劇場版の小学校の時の華恋ちゃんは着ています。カニ好きなんじゃないですか? だから鍋でもカニで。真矢もカニ好きそうですし。すみません、いい加減で......。
--いえいえ、確かに。
古川:あと、そういうキャラクターに関して重要なことが僕の中に1つあって。「見たことのない生き物」のデザインは結構難しいんですよ。説明が必要になっちゃう。もしくは徹頭徹尾説明しないことによって演出するしかない。でも、カニなんだって言ったらカニじゃないですか。クマなんだって言ったらクマじゃないですか。
三森すずこさんの一言で元気になった
--色々お話を伺っていると、最初の舞台やキャストを源泉にして、『レヴュースタァライト』全体のいろんなものが生まれてきた部分もあると感じたのですが、具体的にキャストとのやり取りで印象に残ったことはありますか。
古川:なにをもって印象的とするかですよね。愚にも付かないくだらない話なのですが、テレビアニメのアフレコの時に、グロッキー状態で僕が座っていたことがありまして。その時に(神楽ひかり役の)三森すずこさんに「おはようございまーす。監督大丈夫ですか」って言われて、「まあ、生きてるだけです」って言ったら、三森さんが「生きててよかった~」とおっしゃって。その時に「はあああ〜〜〜」って元気になって、「え? すごい、スターだ!」と。僕みたいな特にこの世に必要のないオジサンが「ふわああ」と元気になって「あ〜生きててもよかったんだ、おれ」と思って。「なんてこった、この人は他人に自己肯定感を与えた!」ってびっくりしちゃった。その時、「これが本物の華のある役者さんが持つ力なのか」「不思議な力だな」と思いました。
三森さんが持つ「陽の力」を思いっきり感じました。自分が語り足りてないせいで、また物語の性質上、ひかりが陰な雰囲気っぽくなってしまったのですが、テレビアニメ8話や劇場版エンディングのひかりって個人的にはすごく陽のイメージなんです。そこは、三森さんの陽のオーラに引っ張られている雰囲気がありますね。華恋に対しても良い意味ですごくサバサバしているのではないかと。で、華恋は華恋で「お疲れ〜!またね!」と返しているのではないかと思っています。映画のラストのスカッとした読後感は狙ったものでもありますが、作品・キャスト・スタッフとの歩みの結果からなのかもしれません。
(後編に続きます)
2022.06.24